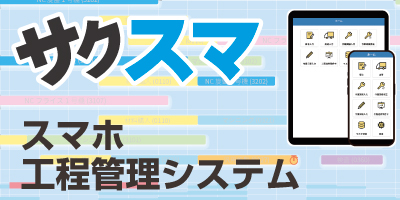システム導入は機能比較だけでは不十分―失敗する理由と現場で使えるシステムの見極め方
システム導入を検討する際、多くの企業が最初に取り組むのが「機能比較表」の作成です。
A社の製品は見積機能がある、B社の製品は図面管理ができる…といった具合に○×を付けていけば、一見すると合理的な判断ができそうに思えます。
しかし、こうした「機能比較」だけを根拠に導入を決めてしまうと、現場では使いにくく結局活用されない、といった失敗につながることもあります。
実際、多くの企業が「システムを導入したけれど、結局エクセルに戻ってしまった」という苦い経験をしているのです。
このページでは、機能を比較するだけでは失敗する理由と、現場で使えるシステムを見極めるための視点をお伝えします。
A社の製品は見積機能がある、B社の製品は図面管理ができる…といった具合に○×を付けていけば、一見すると合理的な判断ができそうに思えます。
しかし、こうした「機能比較」だけを根拠に導入を決めてしまうと、現場では使いにくく結局活用されない、といった失敗につながることもあります。
実際、多くの企業が「システムを導入したけれど、結局エクセルに戻ってしまった」という苦い経験をしているのです。
このページでは、機能を比較するだけでは失敗する理由と、現場で使えるシステムを見極めるための視点をお伝えします。
- システム導入で「機能比較」だけに頼ると失敗する理由
- 機能比較より大切な視点とは
- 現場で使えるシステムの見極め方
システム導入で「機能比較」だけに頼ると失敗する理由
機能比較表は便利ですが、それだけでは導入判断を誤る危険があります。
多機能のほうが便利だろうと思って導入しても、結果として「宝の持ち腐れ」になることも少なくありません。
(例)A社…「見積機能あり」だが、入力が複雑で使いづらい
B社…「見積機能なし」だが、Excelテンプレートとデータ連携で十分に対応できる
〇や×の中身を確認することが重要です。
機能比較は必要ですが、それだけでは「現場で使えるシステム」を見極められないのです。
<よくある失敗パターン>
① 「多機能=優れている」は間違い
機能が多いほど複雑になるため、現場では使いづらい場合もあります。多機能のほうが便利だろうと思って導入しても、結果として「宝の持ち腐れ」になることも少なくありません。
② 「機能表に○の数が多い方が優秀」とは限らない
たとえば、比較表でA社は〇、B社は×になっていたとしても、単純に〇がついている方が良いとは言い切れません。(例)A社…「見積機能あり」だが、入力が複雑で使いづらい
B社…「見積機能なし」だが、Excelテンプレートとデータ連携で十分に対応できる
〇や×の中身を確認することが重要です。
③「自社の業務」が不明確なまま比較している
根本的な問題として、自社の業務や課題が整理できていないまま機能比較を始めるケースも多く見られます。
- 現在の業務のどこが問題なのか?
- その問題はシステムで解決できるのか?
- システム導入以前に業務ルールを見直した方がいいのか?
機能比較は必要ですが、それだけでは「現場で使えるシステム」を見極められないのです。
機能比較より大切な視点とは
システム導入を成功させるためには、実は製品そのものよりも「誰と進めるか」が重要です。
| 見るべき項目 | 選定を成功させる視点 |
|---|---|
| パッケージに入っている機能 | 自社業務に合うか、使いやすいか |
| システム会社の対応 | 業務を理解し、課題に寄り添っているか |
| 提案者の質 | 「本質的な解決」を提案してくれるか |
現場で使えるシステムの見極め方
1. 提案者は実際の運用イメージを示してくれるか
カタログを見せるだけでなく、自社データを用いたデモや試験導入を通じて、具体的にどの機能で業務がどのように改善するかを提示できるか見定めましょう。2. 業務フローを理解しているか
提案者が自社の業務を理解し、場合によっては「業務の進め方を変えた方がよい」と進言できるなら、信頼に値します。システムは本来、業務改善とセットで導入されるべきものです。
3. 導入後の伴走サポートがあるか
初期設定やトラブル対応、追加要望に柔軟に対応できる体制があるか確認しましょう。導入後も寄り添ってくれるかが、システム定着の成否を分けます。
まとめ:システム導入の成否を決めるのは「人」
システム導入において、機能比較は出発点に過ぎません。
戻る
- 「機能が多い=良い」とは限らない
- 機能比較表の○の数より「現場で使えるか」が重要
- 機能比較の前に自社の業務の整理が必要
- 機能だけでなく、ベンダーの担当者・対応力を比較