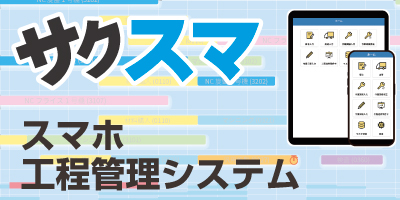パッケージソフトの失敗しない選び方―多機能より「現場が使える」が正解
業務効率化やデジタル化のためにパッケージソフトの導入を検討する企業が増えています。
しかし、導入後に「思っていたのと違った」「現場が使ってくれない」という声も少なくありません。
このページでは、ソフト選定に失敗しないために知っておきたいポイントをご紹介します。
・ わかりにくい「多機能」パッケージソフトの問題点
・ 失敗を招きやすいパッケージソフトの選定フロー
・ 「現場が使える」パッケージソフトとは?
わかりにくい「多機能」パッケージソフトの問題点
わかりにくく使いづらいパッケージソフトは、以下の3つの問題点を抱えています。
① ユーザーの要望を採り入れすぎて複雑化した
過去の導入先からの要望を積み重ねた結果、機能・ボタン・メニューが乱立したソフトになっているケースが多々あります。「この機能はA社の要望」「こっちはB社」「これはC社」……
こうして何のための画面かわからないものができあがり、初めて触れるユーザーは戸惑います。
「多機能だけど使いにくい」問題を引き起こす典型例です。
② 対応生産形態を増やしすぎて肥大化した
見込生産・受注生産・部品製造・組立製造……これらすべてに対応しようとすると、ソフトはどんどん膨張します。
異なる業態向けの機能を詰め込んで万能になればなるほど、自社にとっての使いやすさからどんどん遠ざかるのです。
「あの画面はうちには不要」「この処理は見込み生産前提だから使えない」
上記のような不満は、対応範囲を広げすぎて誰にも最適化されていない万能ソフトに共通しています。
③ 生産管理を理解していないSEが設計した
UIや機能設計において、業務の流れを知らないエンジニアが作ると、現場にとって非常に使いにくいものになります。× 製造番号の入力タイミングが不自然
× 在庫があるはずなのに引当できない
× 仕掛品や戻り品が考慮されていない
SE視点で理論が整っていても、現場業務に合っていなくては使えません。
現場はストレスを抱えながら日々の入力や確認作業を行うことになります。
もし、説明に来たベンダー担当者が「その機能がなぜ必要なのか」「どの業務課題に効くのか」まで説明できない場合は、
自社のソフトがどの業態のどのような課題を解決できるか理解できていません。
その場合、上記のように複雑化・肥大化した現場業務にフィットしないソフトである可能性が高いと言えます。
失敗を招きやすいパッケージソフトの選定フロー
選定フローが適切でない場合、導入後に「思っていたのと違う」「現場で使えない」といった失敗に直結します。
特に以下のような流れで進めてしまうと、高確率で問題が発生します。
<失敗パターンの選定フロー>
1. 経営判断のみでスタート
現場の意見や実務の課題をヒアリングせず、「DXを進めたい」「とりあえず導入したい」といった経営層主導で検討を始める2. 営業資料やデモだけで判断
ベンダーが用意した見栄えの良い資料や画面デモを見て、「これなら良さそう」と早期に候補を絞ってしまう3. 業務フローとの整合性を検証しない
ソフトが自社の業務プロセスと合致しているかを検討せず、「カスタマイズすれば対応できるだろう」と安易に進める4. カスタマイズ前提の導入方針で予算が膨張
安易な選定によって標準機能では回らず、個別対応の要望が多発して予算と納期が想定を超える特に製造業のように部門をまたいだ運用が必要な現場では、不完全な選定フローを踏むことで、
「誰も使わないシステム」ができあがるリスクが非常に高くなります。
「現場が使える」パッケージソフトとは?
パッケージソフト導入を成功させるための鍵は、「現場が使える」ことにあります。
どんなに多機能・高機能でも、現場が使わなければ意味がありません。
<「現場が使える」ソフトの特徴>
✓ 1週間以内で大枠をつかめる✓ 画面がすっきりしていて直感的な操作で使用できる
✓ 自社に必要な機能がしっかり用意されている
✓ 他のシステムと連携できる
日常業務の延長線上にあるシステムこそが、選定すべきパッケージソフトです。
✓ 1週間以内で大枠をつかめる
使えるソフトは、システム担当者が1週間くらい使えば大まかな流れを理解できるような「分かりやすい設計」になっています。逆に、2〜3か月かかるようなソフトは現場で運用されることはほぼありません。
✓ 画面がすっきりしていて直感的な操作で使用できる
パッと見て「何をする画面か」がすぐわかるソフトは使いやすいソフトです。項目が多すぎてゴチャゴチャしていると、現場が直感的に使えません。
複雑なマニュアルを読み込まなくても簡単に入力でき、必要な情報がすぐに検索できるか確かめましょう。
✓ 自社に必要な機能がしっかり用意されている
多機能であることよりも自社に必要な機能を備えていることが重要です。<機能例>
・ 品目コード・ロット番号・担当者などが入力できる
・ 作業実績の登録が簡単にできる
・ ステータス(未着・完了など)が見やすい
自社に必要な機能を現場と共有できていれば、失敗せずに選べます。
✓ 他のシステムと連携できる
現場ではExcelなど他システムとやりとりすることも多いため、以下のような機能があるとさらに便利です・ 項目名称の変更(「製番 → 工事番号」に変えるなど)
・ マスタデータの取込
・ 作業実績・受注・予算などのデータ取込
・ Excelへの出力
・ 他システムへのデータ連携(CSVやAPI)
まとめ:自社にとって「使えるソフト」こそが正解
ソフトを導入する目的は「業務を改善すること」「現場をラクにすること」です。
「多機能」よりも「必要十分」で「現場が迷わず使える」パッケージソフトなら、その目的を果たせます。
| 使えないソフト | 使えるソフト | |
|---|---|---|
| 画面 | 多機能すぎてゴチャゴチャしている | すっきりしていて何をする画面かがすぐにわかる |
| 設計 | 業務の流れを理解していないSEが設計している | 現場の流れに合わせてつくられている |
| 機能 | 多機能だが不要なものも多い | 自社に必要なものがそろっている |
| 教育期間 | 覚えるのに数カ月かかる | 1週間程度で全体像がつかめる |
自社業務とのフィット感や今の課題を確実に解決できるかを見極めて、最適なパッケージソフトを導入しましょう。
戻る